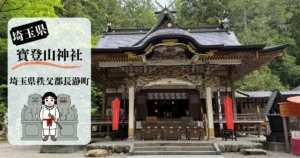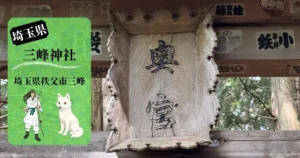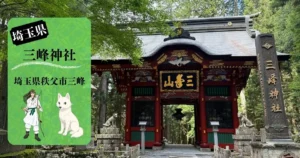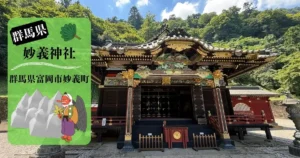こんにちは、あちです。
今回は、栃木県足利市に鎮座する「伊勢神社」をご紹介します。
平安時代の仁平元年(1151年)に創建されたと伝えられ、天照大御神と豊受大御神の二柱をお祀りする由緒ある神社です。
足利氏をはじめ、源氏の流れをくむ武士たちから信仰を集めてきたことでも知られ、地元では「足利のお伊勢さん」として親しまれています。
この記事では、足利伊勢神社の歴史やご祭神、境内の見どころを具体的に分かりやすく解説します。
これから参拝を予定している方や、神社の背景を知りたい方の参考になれば幸いです。
✔足利伊勢神社の由緒と信仰
✔ご祭神の概要
✔境内の見どころ(内宮・月読宮など)
✔御創建八百七十年記念事業
✔アクセスと駐車場情報
この記事では、正式名称は「伊勢神社」ですが、地元では親しまれている通称「足利伊勢神社」としてご紹介していきます。以降、「足利伊勢神社」と表記しますのでご了承ください。
足利伊勢神社って?

足利伊勢神社は、栃木県足利市にある、歴史ある神社です。
古くから地域の信仰を集めてきました。
足利伊勢神社の由緒
足利伊勢神社は、平安時代中期の仁平元年(1151年)に創建されたと伝えられています。
当時この地は「足利庄伊勢宮」と呼ばれ、天照皇大神をお祀りするお社として、源氏の流れをくむ足利氏や新田氏などから厚く信仰されてきました。
鎌倉時代の文書には、足利氏の祖・貞氏が伊勢宮の祭祀について「武運長久を祈るお社であるため、怠りなく務めるように」と指示していた事が記されており、当社の重要性がうかがえます。
江戸時代後期の弘化2年(1845年)には社殿が再建され、明治期にも整備が進められました。
しかし、大正14年(1925年)の町の大火により社殿などが焼失。
その後、氏子や崇敬者の尽力によって、昭和4年(1929年)に神明造の様式で現在の社殿が再建されました。
昭和17年(1942年)には村社に指定され、現在も「足利のお伊勢さん」として地元の信仰を集め続けています。
足利伊勢神社のご祭神・ご神徳
| 神名(よみがな) | ご神徳(ご利益) |
| 天照皇大神 (内宮) あまてらすすめおおかみ | 皇室の祖神として広く信仰される神。国家安泰や暮らしの安定、日々を健やかに過ごすことを願う対象として信仰されています |
| 豊受皇大神 (外宮) とようけのすめおおかみ | 衣食住や産業を司る神。五穀豊穣や商いの安定、日々の生活が滞りなく続くことを願う信仰があります |
| 月讀命 (月讀宮) つきよみのみこと | 月の神として知られ、時の巡りや自然の調和を象徴する存在。月の満ち欠けになぞらえ、子授けや安産を願う信仰が見られます |
※上記のご利益は、一般的に信仰されている内容であり、すべての方に効果を保証するものではありません。
足利伊勢神社の見どころ

出典:足利伊勢神社 境内配布マップより
内宮

内宮でお祀りされている神様は天照皇大神です。
天照皇大神は、どんな神様?
(タップして開く)
| 神名 | 天照皇大神 |
| 読み仮名 | あまてらすすめおおかみ |
| 主なご神徳 | 国家安泰、家内安全、開運招福 |
| ご神徳の特徴 | 太陽の神として、万物を照らし育む力を持つ。皇室の祖神であり、日本の総氏神ともされる |
天照皇大神は、「古事記」や「日本書紀」に登場し、日本神話の中でも最も高貴とされる女神です。
太陽の神として万物を照らし育てる力を持ち、皇室の祖神ともされており、伊勢神宮の内宮でもお祀りされています。
「天岩戸」の神話では、弟・須佐之男命(すさのおのみこと)の乱暴を受けて岩戸に隠れたことで、世界が闇に包まれたと伝えられています。
しかし、八百万の神々の協力によって再び岩戸から姿を現したことで、世界に光が戻ったとされます。
この神話は、太陽の再生と秩序の回復を象徴する重要な物語とされ、日本人の精神文化にも深く関わっています。
足利伊勢神社の社殿は、これまでに何度も再建されてきた歴史があります。
江戸〜明治にかけての再建
江戸時代後期の弘化2年(1845年)、社殿の復興造営が行われました。
明治14年(1881年)には、伊勢神宮を遠くから拝むための「遥拝所(ようはいじょ)」として再建されました。
これは、当時の人々が伊勢神宮まで行かずとも信仰を続けられるよう設けられた施設です。
さらに明治35年(1902年)には本殿が新築され、明治39年(1906年)には社殿の再興が実施されました。
大正時代の「お木曳行事」
大正2年(1913年)には、伊勢神宮の御用材を使った社殿の建築にあたり、「お木曳行事(おきひきぎょうじ)」が足利町で盛大に行われました。
当時は町民が総出で参加し、地域一体となった大規模な行事だったと伝えられています。
大火と再建、現在の社殿へ
大正14年(1925年)の大火により、社殿や社務所などが焼失。
その後、氏子たちの尽力によって再建が進められ、昭和4年(1929年)に現在地での新築が完了しました。
神明造の建築様式
再建された社殿は、伊勢神宮の正殿を模した神明造(しんめいづくり)の建築様式で造られています。
まっすぐな柱や梁を使い、簡素で直線的な構造が特徴とされています。
外宮

外宮でお祀りされている神様は豊受皇大神です。
豊受皇大神は、どんな神様?
(タップして開く)
| 神名 | 豊受皇大神 |
| 読み仮名 | とようけのすめおおかみ |
| 主なご神徳 | 衣食住の守護、農業・穀物の守護 |
| ご神徳の特徴 | 生活安定や産業繁栄を象徴する衣食の守り神 |
豊受皇大神は、『古事記』『日本書紀』に登場する神で、食物や穀物を司る神様として知られています。
もともとは丹波国(現在の京都府北部)にお祀りされていた神ですが、天照皇大神の食事を司る役割を担うため、神様の意志により伊勢に迎えられたと伝えられています。
人々の衣食住を支え、生活の根本を象徴する神であり、暮らしの安定や発展を願う信仰の対象となっています。
伊勢神宮・外宮の主祭神としても広く知られており、「外宮先祭」の慣わしでも知られる農業・産業神として、全国的に信仰されています。

足利伊勢神社には、伊勢神宮と同じく内宮(天照皇大神)と対になる形で「外宮(げくう)」が設けられています。
足利伊勢神社の外宮は大正14年(1925年)の大火で社殿や社務所とともに焼失したのち、昭和4年(1929年)の本殿再建と同時期に整えられたと伝えられています。
お社は小規模ながらも、歴史を感じさせる賽銭箱や佇まいが印象的で、落ち着いた雰囲気の中で手を合わせることができます。
外宮のお社には、白地に花菱紋と巴紋があしらわれた神幕が掛けられています。
赤と紺の帯があしらわれた端正なデザインで、境内の静かな空間によくなじんでいます。
月讀宮

月讀宮でお祀りされている神様は月讀命です。
月讀命は、どんな神様?
(タップして開く)
| 神名 | 月讀命 |
| 読み仮名 | つきよみのみこと |
| 主なご神徳 | 子授け・安産・運気上昇・夜の守護 |
| ご神徳の特徴 | 月の満ち欠けは、生命の誕生に深く関わっていることから、子授け、安産、運(ツキ)気上昇の神とされる |
月讀命は、『古事記』や『日本書紀』に登場する月の神で、天照皇大神・須佐之男命とともに伊弉諾尊(いざなぎのみこと)から生まれた三貴子の一柱です。
天照皇大神が太陽を、須佐之男命が海を司るのに対し、月讀命は夜の世界や月を象徴する神とされ、「時間」や「静けさ」とも関わりが深いと考えられています。
また、月の満ち欠けは生命の誕生や安定と関わるため、子授け・安産・運(ツキ)の神としても信仰されています。
月讀命は他の神々と比べて祭祀が少ない一方、月の神として静かに崇敬されており、各地にひっそりと祀られる例も見られます。

月讀宮は、境内の一角にひっそりと佇む小さなお社です。
石段を上がった先には、月をかたどった紋が施された奉納幕が掛けられており、月讀命をお祀りする社にふさわしい落ち着いた雰囲気を感じさせます。
お社の左手の壁面には、子授けや安産を願う絵馬が丁寧に結びつけられていました。
稲荷社

月讀宮のすぐそばには、稲荷大神をお祀りする小さな石祠があります。
五穀豊穣や商売繁盛を願う神様として広く信仰されており、月讀命への参拝とあわせて手を合わせる方も多く見られます。
手水舎

拝殿の手前には、木造の屋根を備えた手水舎が設けられていて、参拝前に身を清める場所として整備されています。
水盤は複数の自然石を組み合わせた造りで、素朴ながらも趣があり、境内の落ち着いた雰囲気によく調和しています。
回漕問屋忠兵衛の石燈籠

境内には、大正14年(1925年)に伊勢神社が現在の場所へ移ったときに、回漕問屋・忠兵衛が奉納した石燈籠が移されています。
この石燈籠は、江戸時代の舟運文化を今に伝える貴重な歴史資料でもあります。
平成23年に発生した東日本大震災の影響で倒壊したため、保存修理が行われ、現在は上下を分離した形で設置されています。
石燈籠の詳細(境内案内板より)
(タップして開く)
足利市重要文化財(考古資料)
回漕間屋忠兵衛の石燈籠 一基 伊勢神社
総高 三七五・〇cm
建立 嘉永二年(一八四九)問屋忠兵衛は、江戸時代、足利・桐生の外港として廻米と織物の輸送業務で繁栄した「北猿田河岸」の中で、最も古い歴史をもつ回漕問屋であった。
本石燈籠は、問屋忠兵衛が御神燈として「船中安全」を祈願して嘉永二年(一八四九)に建てたものである。
安山岩質で上から宝珠、笠、火袋、中台、竿(創建当初は二段であったと考えられる)、反花付基壇、基壇二段と高さ九〇cmの石台から成る。
協賛者の陰刻からは近畿地方にまで及ぶ当時の広範な商域を知ることができる。
「問忠」(問屋忠兵衛の略称)廃業後の明治二十年(一八八七)に、両毛鉄道足利駅近くの伊勢宮(当時)に移設され、大正十四年(一九二五)、伊勢神社の現在地移転に伴い現位置に移設された。
江戸時代、足利・桐生の舟運の外港であった「北猿田河岸」の繁栄の様子を具体的に示す考古資料として貴重である。平成十九年十一月十五日指定
足利市教育委員会
引用元:足利伊勢神社 境内案内板(足利市教育委員会)
御創建八百七十年記念事業

(※2025年4月6日現在の状況です)
足利伊勢神社では、「伊勢の遥宮 次の100年へ〜これからの伊勢宮×未来への継承〜」を掲げ、御創建八百七十年を記念した社殿修繕および境内整備事業が進められています。
これは、伊勢の遥宮(とおのみや)としての信仰の歩みを、次の100年へとつないでいくための取り組みとして行われているものです。
今回の記念事業によって、境内がどのように整えられていくのか、これからの変化が楽しみです。
遥宮とは?
(タップして開く)
「遥宮」とは、伊勢神宮の内宮や外宮などの本宮から離れた地に鎮座し、深いつながりを持つお宮を指す言葉です。
代表的な遥宮には三重県内の瀧原宮(たきはらのみや)や伊雑宮(いざわのみや)などがあり、いずれも天照大御神の御魂(みたま)をお祀りする格式の高い別宮として知られています。
また、伊勢神宮と深いつながりを持つ神社が遠隔地に建立された場合にも「遥宮」と呼ばれることがあります。
たとえば、東京都文京区にある小石川大神宮は、伊勢神宮から約400km離れた地にありながら、その信仰的な結びつきから遥宮と位置づけられています。
このように、「遥宮」とは、単なる地理的な距離だけでなく、伊勢神宮との信仰的なつながりを保ちながら、離れた地に祀られる特別なお宮のことを指します。
再訪時の境内の様子(2025年夏・追記)
今回、再び参拝したときには、御創建八百七十年記念事業の工事がだいぶ進んでいて、境内の雰囲気にも変化を感じることができました。
新しく整えられたところを、写真とあわせてご紹介します。

本社と社務所の間には細かな砂利が敷かれていて、広い空間がよりすっきりとした印象に。
歩くとサクサクと音がして、参拝に心地よさを感じました。

この新しく整備された空間が、これからどんなふうに育ってどんな表情に変わっていくのか、参拝のたびに確かめる楽しみがひとつ増えました。

境内には「蹲(つくばい)」も新しく設けられていました。
「振りつくばい」と呼ばれるものだそうで、地面を深く掘り下げて据えられた手水鉢だそうです。
土壌の改良も一緒に行われ、浅間石や竹炭を使って水はけが良くなるように工夫されていました。

さらに、十月桜や蝋梅の植樹も進められていて、これから四季ごとに境内を彩っていくのが楽しみです。
境内にある石蔵もきれいに修繕されていました。

大正14年に大谷石で築かれた建物で、今回の改修によって当時の趣を残しながらもしっかりと整えられていて、とても印象的でした。
今回の再訪では、境内全体が「未来に向けて整備されている途中」なんだなと実感しました。
これから年月を重ねる中で、植えられた木々や新しく加わった設備が、どんなふうに境内に馴染んでいくのか、とても楽しみです。
※追記レポートはここまでです。
社務所

足利伊勢神社の社務所では、お守りやご朱印を受けることができます。
なかでも、絹織物「足利銘仙(めいせん)」を使用したお守りや、中身が透けて見える月讀宮の「福守り」など、特徴ある授与品が揃っています。
足利伊勢神社の授与品やご祈祷については、別記事で詳しくまとめています。
授与品関連記事はこちら
ご祈祷関連記事はこちら
足利伊勢神社の基本情報と交通アクセス・駐車場
基本情報
| 神社名 | 伊勢神社 (いせじんじゃ) |
| ご祭神 | 天照皇大神 (あまてらすすめおおかみ) 豊受皇大神 (とようけのすめおおかみ) 月讀命 (つきよみのみこと) |
| ご神徳 | 家内安全、五穀豊穣、商売繁盛、厄除開運など |
| 創建 | 仁平元年(1151年) |
| 主要祭事 | 例大祭(7月17日)、春季大祭(4月17日)、秋季大祭(10月17日)、他 |
| ご朱印 | 社務所にて授与(初穂料500円) ※授与時間・詳細は別記事にてご紹介しています |
| 所在地 | 栃木県足利市伊勢町2-3-1 |
| TEL | 0284-41-5347 |
| 受付時間 | 9:00〜16:00 |
| 駐車場 | 無料駐車場あり (神社敷地内約15台、ほか徒歩2分ほど/約10台) |
| トイレ | 境内にトイレはありません |
| 公式SNS | X(旧Twitter)/足利伊勢神社 Instagram/足利伊勢神社 facebook/足利伊勢神社 |
交通アクセス
| 車の場合 | 北関東自動車道 足利ICから約12分 詳細はNEXCO東日本ホームページをご確認ください |
| 電車の場合 | JR両毛線 足利駅(北口)から徒歩約3〜4分 東武伊勢崎線 足利市駅(南口)から徒歩約20〜25分 ※最新の運賃やその他詳細は JR東日本えきねっと 東武伊勢崎線|東武鉄道公式サイトでご確認下さい |
| 地図 | Googleマップで見る |
駐車場

足利伊勢神社には、参拝者向けの無料駐車場が2カ所あります。
①神社社務所前の駐車場(約15台)
社務所の前に、舗装された駐車スペースがあります。
祭事などがない場合は、こちらの駐車場を利用すると便利です。
②伊勢神社専用駐車場(約8台)
御創建870年記念事業のひとつとして整備された駐車場です。
神社からは徒歩1分ほどの場所にあり、こちらも参拝者が利用できます。
現地には「伊勢神社専用駐車場」の看板が設置されており、Googleマップでも「伊勢神社駐車場」と表示されるため、場所は分かりやすいです。
まとめ
伊勢神宮とご縁の深い足利伊勢神社。
伊勢神宮の遥宮として信仰されてきた神社で、創建は平安時代の仁平元年(1151年)と伝えられています。
境内には月讀命を祀る月讀宮のほか、江戸時代の舟運文化を伝える石灯籠(足利市重要文化財)もあります。
JR足利駅(北口)から徒歩3分ほどとアクセスも良好。
この記事が、足利伊勢神社を訪れる際の参考になれば幸いです。
他の神社紹介記事はこちら
本記事の由緒・ご祭神・ご神徳・彫刻・境内社等に関する情報は、栃木県神社庁公式ホームページ「伊勢神社」や足利伊勢神社SNS(X旧Twitter)、境内の案内板および関連資料をもとに構成しています。(2025年4月時点の公開情報に基づく)
なお、境内配布マップの写真については、足利伊勢神社様より事前に掲載許可を頂いております。
*その他の内容や表現については、筆者の責任において記載しています。
神名の表記は、「古事記」や「日本書紀」に基づくもの、または一般的な表記を使用しています。ただし、祭神やご神体の名称、ご利益は、地域や神社、神仏習合の影響により異なる場合があります。
神社では、季節や特別な行事にあわせて限定のご朱印やお守りが授与されることがあります。また、頒布を終了した授与品もある可能性があります。最新の授与品情報については、社務所・公式サイト・SNS等をご確認下さい。